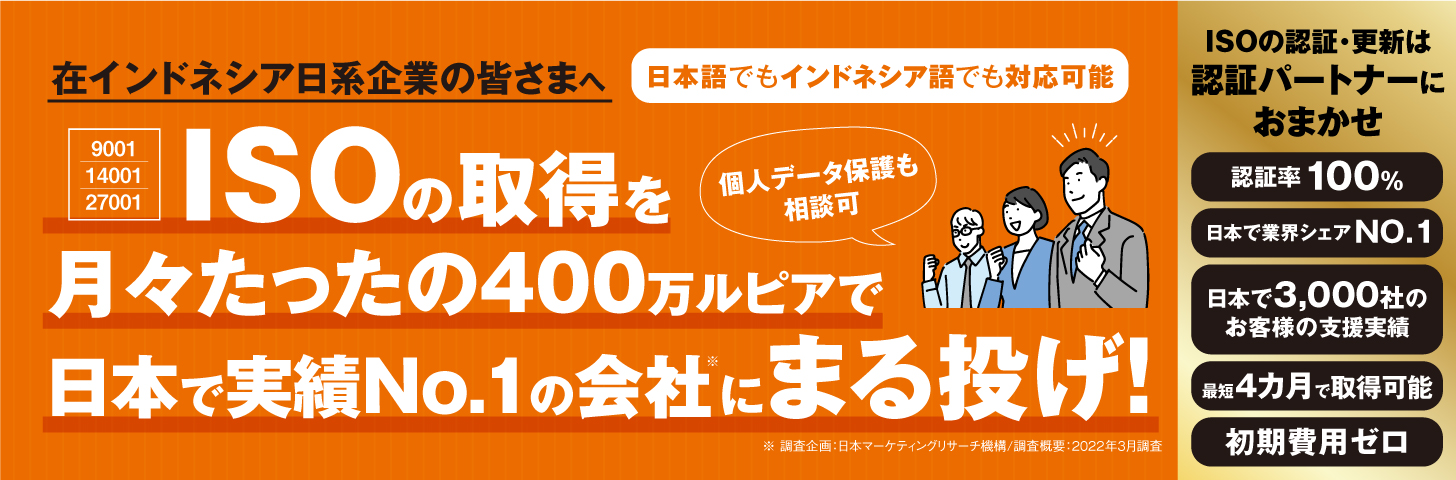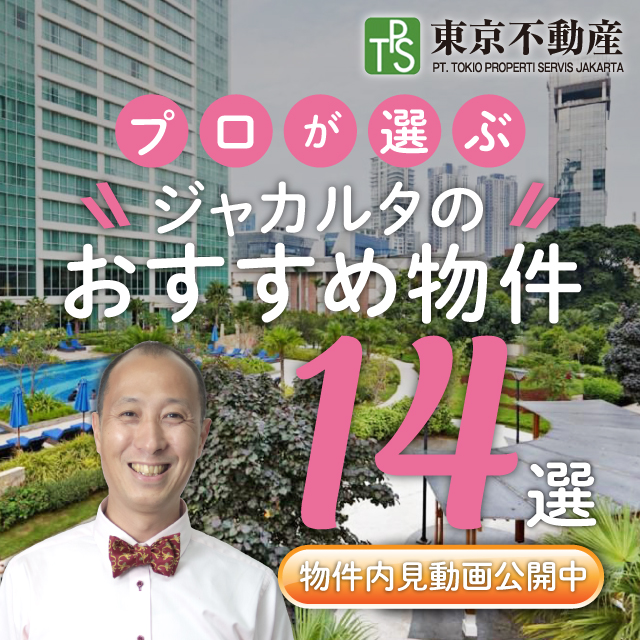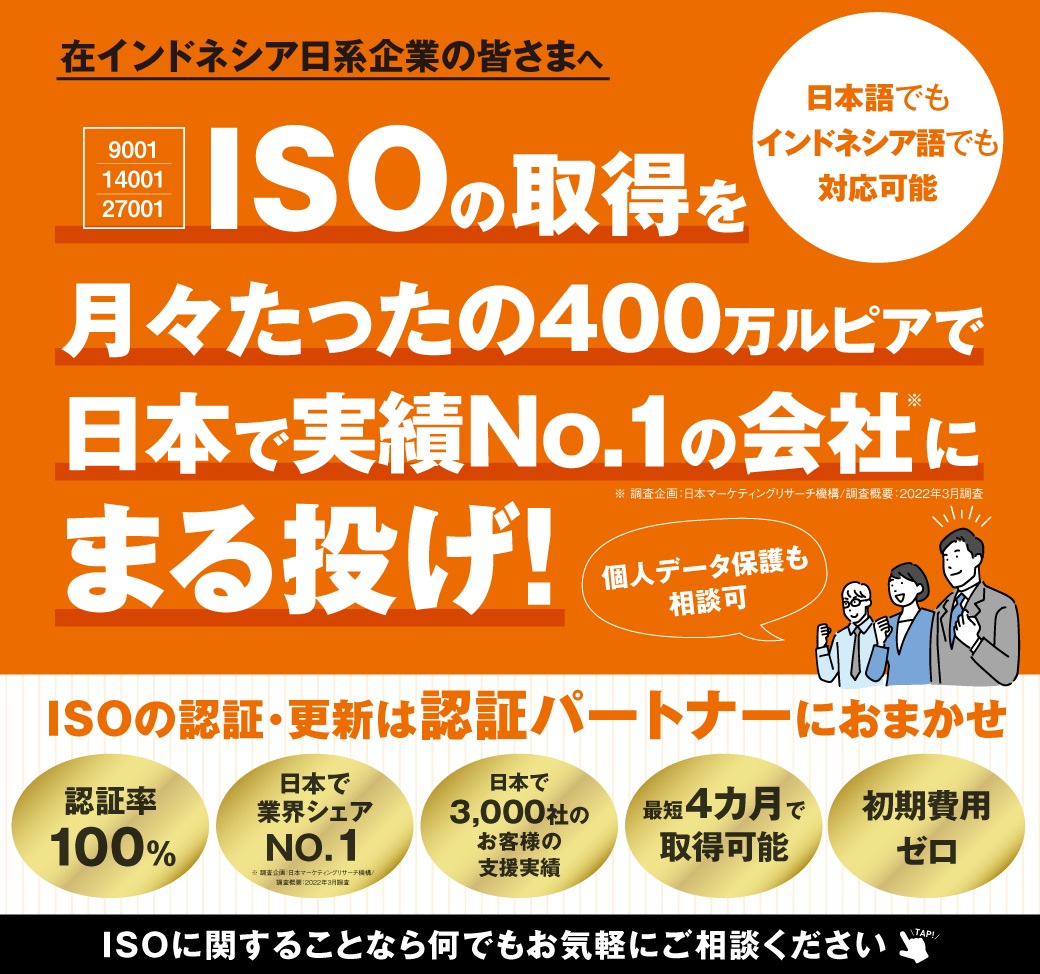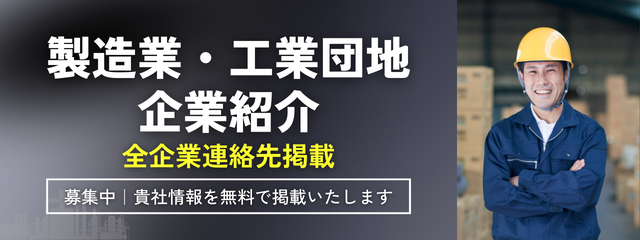目次
人口ボーナス期があと15年続く
インドネシアは総人口に占める生産年齢人口比率が上昇する期間である「人口ボーナス期」が2030年まで続くとされています。この時期には労働力増加率が人口増加率を上回ることで、経済成長が後押しされます。人口ボーナス期にある国は消費の活発化による高い経済成長を実現する潜在的な能力を持ちます。
また、これにより中間所得層が増えることも期待されています。2009年に中間層が8000万人(全人口比35%)、低所得層が1億5000万人 だったのが、2015年には中 間層と低所得層の人口が逆 転、2020年には中間層が1億 9000万人と全人口に占める 割合が73%にも達します。
統計上の人口ボーナス期
「人口ボーナス期」は統計上で生産年齢人口(15〜64歳)÷ 従属人口(15〜64歳を除く)が 「2」以上の状況を指します。ちなみに 日本は1995年に人口ボーナス期を終えたほか、中国は2015年で終わり、以後は「人口負担期(または人口オーナス期)」に入る。
中間所得層とは
製造拠点としての魅力と問題点
インドネシアで生産年齢人口が増えるということは、廉価な労働力が次々と生まれることを意味します。労働集約型の工場な ら、これまで自給自足に近いような生活を送っていた人々にも新たな雇用機会を創出できるわけです。
一方、製造拠点としてみると電力や道路の整備などインフラ の不足や従業員に対する訓練要員の不足といった問題点を抱え ています。これらの課題があっても、「廉価で豊富な労働力」には高い魅力を感じることでしょう。
長所と短所との折り合いを付けながら拠点を運営していくことになるのではないでしょうか。
自動車・二輪車の需要はほぼ一巡

自動車は2009年から2013年までは右肩上がりでしたが、 2014年にわずかに減少。2015年には前年比16%減にとどまりました。一方、二輪車は2010〜14年に700万〜800万台で推移していましたが、15年に684万台と18%減っています。これは、国内景気の低迷に加え、不完全就労者が金融機関に対してローンを組めず、バイクなどを買いたくても買えないという事情があったことから、急激な落ち込みが起こりました。
その後、2016〜17年にかけては、四輪車に関しては増加傾向に転じましたが、二輪車は需要が一巡したという背景もありほぼ横ばいにとどまっています。
車が買える所得水準
一般的に一人当たりの国内総生産(GDP)が1,000米ドルを超えると二輪車が、3,000米ドルを超えると自動車がそれぞれ買えるようになると言われています。インドネシアの一人当たりGDPは3,531 米ドル(2014年)に達しており、自動車が買えるレベルまで生活水準が上がっているといえます。
モダントレードが急速に拡大
日用品や食品の販売チャネルがマーケットや街角にある小さなお 店などによる「トラディショナルトレード(伝統的な小売業態)」だけでなく、スーパーやコンビニ、デパートといった「モダントレード(近代的な小売業態)」の占める割合が急速に伸びています。この拡大傾向はさらに顕著に進むとみられています。
急成長するインドネシアの小売市場
経済成長による所得水準の上昇で、日用品や食品を中心に消費額が大きく拡大しています。日用品は、人々が美しく衛生的に きれいに暮らすために美容関連、衛生用品、シャンプーなどのパーソナルケア用品、洗剤などのホームケア商品などが急激に伸 びています。一方、食品では加工食品の伸びが著しいほか、各種飲料の消費も大幅に拡大しています。
E-commerceが盛んに
インドネシアではスマートフォンの普及でE-commerceが急激に拡大しています。通信・情報省によるとE-commerceの市場規模は2014年に120億米ドルでしたが、2016年に200億米ドルまで拡大しました。
顕著なE-commerceの例としては、バイクタクシーの予約アプリ「GO-JEK」などがあります。
交通アプリの紹介についてはコチラをご覧ください