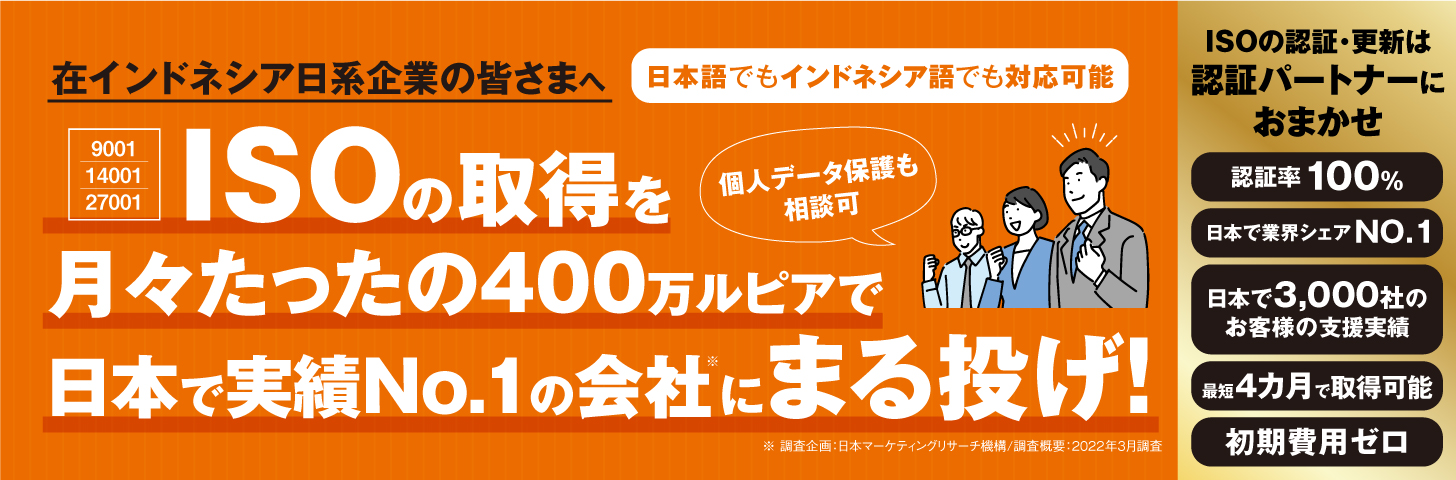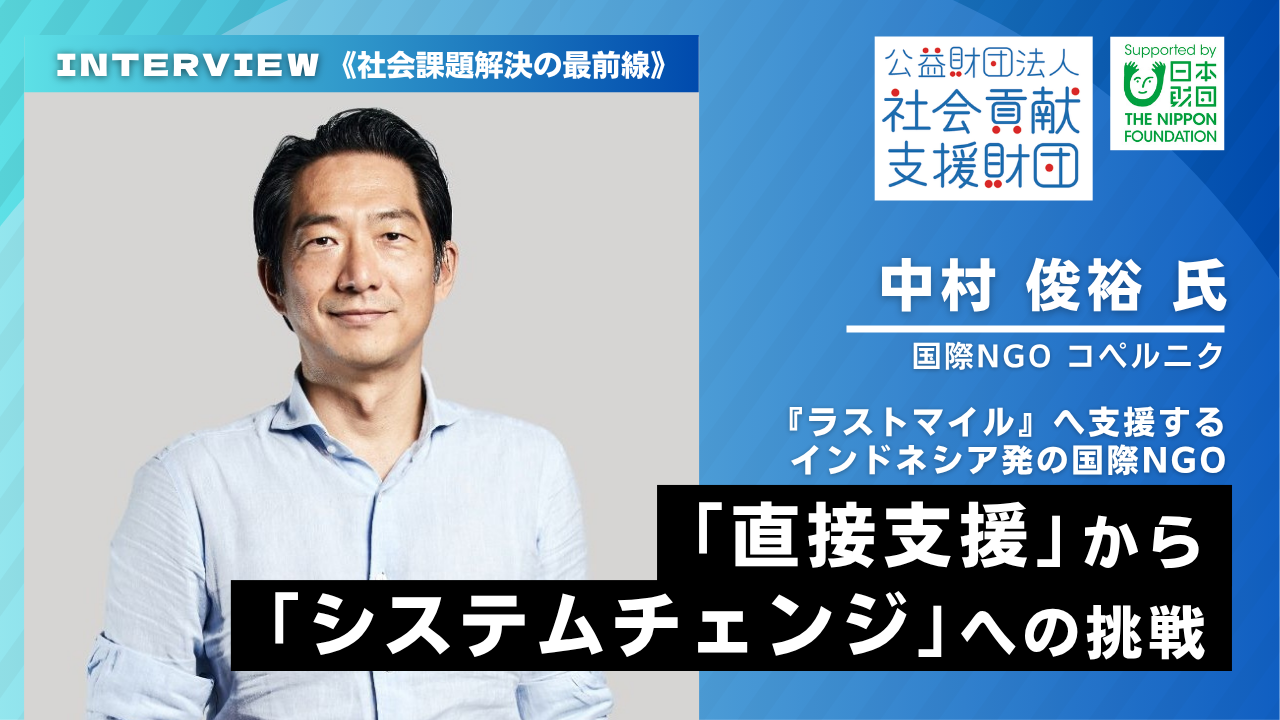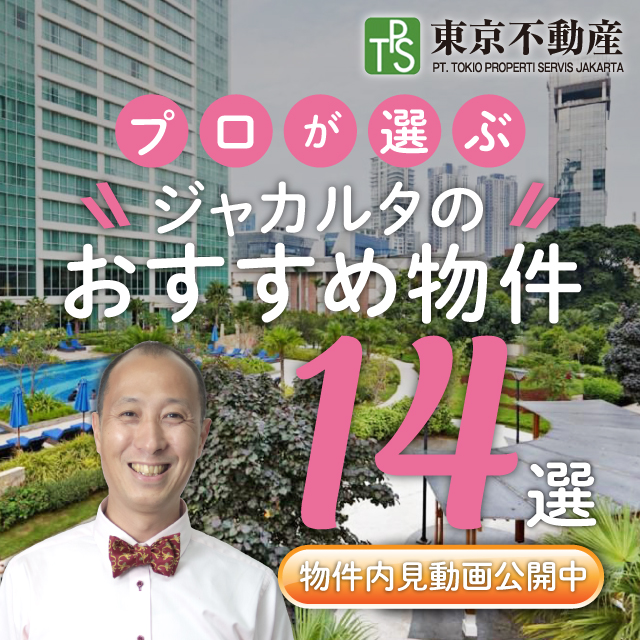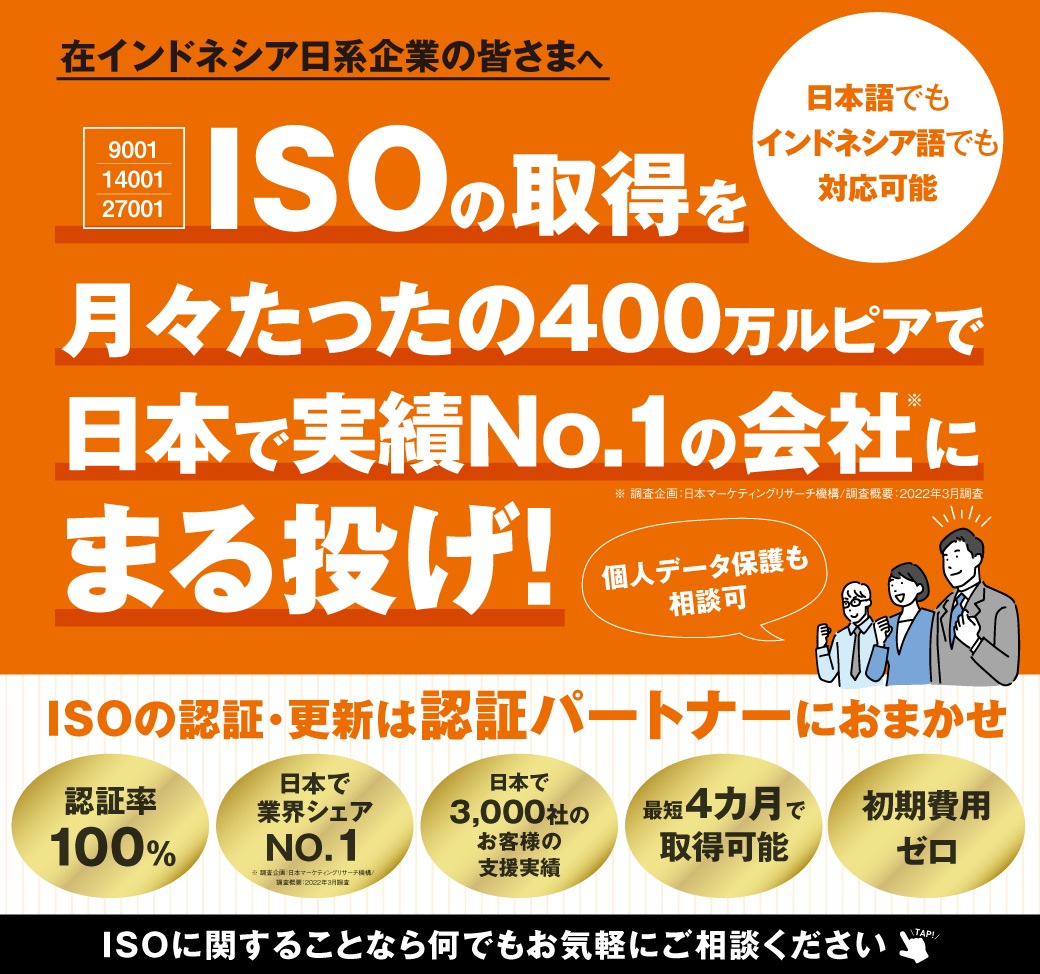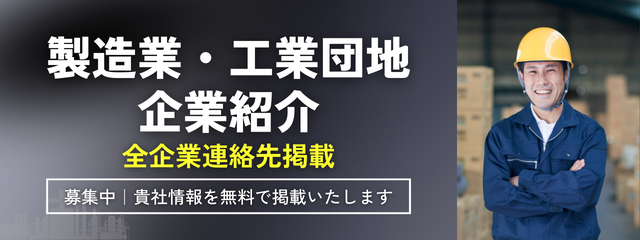<<第60回社会貢献者表彰受賞 コペルニク共同代表 中村俊裕氏インタビュー>>
コペルニクは、「ラストマイル」と呼ばれる僻地で社会課題解決に取り組む国際NGO。共同創設者兼CEOの中村俊裕氏は、国連での経験を経て2010年にコペルニクを設立し、「途上国の課題をいかにスマートに解決するか」を追求してきた。現在は「社会・環境課題解決のためのR&Dラボ」として革新的な挑戦を続けている。「ソリューションズカタログ」による外部団体への知見の共有や、プロジェクトの別法人化による「スピンオフ」を推進することで 、持続可能でよりインパクトの大きな社会変革のムーブメントを創出することを目指しているという。コペルニクのユニークなアプローチと今後の展望を中村氏にインタビューした。
話者プロフィール
コペルニクの活動理念、ラストマイルへのこだわり
ライフネシア:コペルニクが「最も支援が届きにくい地域」を意味する「ラストマイル」に設立当初からこだわり続けていらっしゃる理由についてお聞かせいただけますでしょうか。
中村氏:はい。基本的に、なかなか支援が行き届かない場所で活動できないか、というのが我々の大きな根幹にあります。どうしてもドナーが視察に行きやすいような場所が考慮されがちで、アクセスの良い比較的恵まれた地域への支援が多くなってしまう傾向があります。しかし、最も支援が必要とされているのは、やはり行きにくいところ、つまりラストマイルです。我々がどのような価値を出せるかを考えた時、大きな団体がなかなか行かないような場所で、かつニーズが最も大きいところで活動することが、理にかなっていると考えています。貧困率が高いところは、概ねアクセスが難しい場所でもありますね。

ライフネシア:中村様ご自身のバックグラウンドとして、国連での経験がコペルニク設立につながったと伺いました。学生時代から国際支援への思いをお持ちだったのでしょうか?
中村氏:そうですね。私自身は途上国に住んだ経験はなく、日本で育ちました。しかし、高校生の頃に新聞などで国連の活動が報道されており、「こういう仕事はすごくやりがいがありそうだ」というイメージを持ちました。それがきっかけで、開発の分野に入ってみると、実際に非常にやりがいを感じ、様々なアイデアも出てきて、現在のように独立して活動する流れとなりました。
ライフネシア:国連を退職後、拠点をインドネシアにされたのは、国連勤務時代の経験が大きかったのでしょうか?
中村氏:その通りです。東ティモールの独立直後や、津波後のインドネシアでの仕事の経験がありました。コペルニク創設当初は国連本部があるニューヨークにいましたが、そこを拠点にするのは非効率だと感じ、世界中の様々な都市を検討しました。活動する場所へのアクセスが良いこと、インターネットなどある程度のインフラが整っていること、物価が安いこと、人材が集まりやすいかどうか、といった条件を考慮した結果、インドネシアが良いと判断しました。以前の仕事で得た友人たちの助けもあったのも大きいです。
注力するスピンオフ事業、その形態と支援体制
ライフネシア:続いて、コペルニクの活動は「社会・環境課題解決のためのR&Dラボ」と表現されていますが、現在特に力を入れている具体的なプロジェクト事例があればお聞かせください。

中村氏:はい。私たちは、開発分野で一般的な「助成金」に依存したプロジェクトが資金終了とともに終わってしまうという問題意識を持っていました。そうした中で、プロジェクトから派生し、自分たちの計画を超えて「スピンオフ」という形で事業が生まれる事例がいくつか出てきました。これはサステナビリティとインパクトの観点からも非常に良いと考え、この3、4年で意図的にスピンオフに力を入れ始めています。
例えば、「コペルニクハーベスト」という仮称の案件を準備中で、これは農家支援のプロジェクト(ティモールの蜂蜜、パプアのカカオなど)で培った経験を活かし、農産物を市場につなげ続ける役割を独立会社として作ろうとしています。助成金で築いた基盤をビジネスベースで継続し、インパクトを長く維持する形を模索しています。
ライフネシア:スピンオフは、コペルニク内部の職員が手を挙げて独立するパターンが多いのでしょうか?それとも外部パートナーとの協業もあるのでしょうか?
中村氏: 主に内部の職員が「これを自分のビジネスとしてやっていきたい」と法人化するパターンが多いです。しかし、プロジェクトのパートナーが法人化するような例もあります。例えば、バリのコーヒー農家を支援するプロジェクトで、現地の若い農家の方が非常にやる気があり、アグレッシブに進めてくれたため、その方が直接新しい共同組合を立ち上げる形になりました。もちろん、内部チームがやりたいと申し出た場合はそれを支援しますが、プロジェクトを通じて関係構築が進み、信頼できるパートナーであれば、そういった外部連携も積極的に広げていきたいと考えています。
ただ、完全に外部からアイデアだけを募るアクセラレーターのような形はあまり考えていません。我々としては、課題を見つけ、実証実験を行い、ある程度の確信のもとにスピンオフにつなげていくプロセスの方が、理にかなっていると思っています。
ライフネシア:スピンオフ後の支援体制についてですが、会社の設立支援だけでなく、資金調達や経営のアドバイスなど、どの範囲までどれくらいの期間、関わっていくのでしょうか?
中村氏:現在までに4つのスピンオフがありますが、基本的にいずれもかなり密接に関わっています。というのも、スピンオフ企業に対してコペルニクが株式を保有しているからです。創業者のモチベーション維持のためにマイノリティですが、株主として関係性が続いています。外部資金の紹介やクライアントの紹介、戦略策定なども一緒に行うなど、かなり密に支援しています。言わば、株主であり、かつ経営パートナーとして共に活動している形ですね。
多様性への対応とエビデンスに基づいた支援
ライフネシア:インドネシアは多島国家であり、ラストマイルへの支援には文化や言語の多様性など、多くの課題があると思います。こうした課題にどのように向き合い、乗り越えていらっしゃいますか?

中村氏: これらは非常に難しい課題です。現在約70人のスタッフがいますが、スマトラ、パプア、バリなど、多様な地域出身者がいます。プロジェクトを実施する際には、その地域の出身者をチームに入れるようにしています。そうすることで、方言や文化を理解し、現地のコミュニティとの信頼関係を築きやすくなります。そして、最も重要となるのは、コミュニティが必要としていることを、いかにきめ細かく実行できるかという点です。それができれば、たとえ宗教や文化が異なるチームであっても、活動を進めやすくなります。
ライフネシア:実験・検証を通して支援を行うというアプローチは、時に時間やコストがかかる可能性も考えられます。短期間での成果が求められる国際支援の現場において、このアプローチをどのように正当化し、関係者からの理解を得ているのでしょうか?
中村氏: 実は、タイムラグという点ではあまりないんですよ。この分野では、いまだに「ビフォー/アフター」のアセスメントが主流で、そもそも適切な予算配分がされず、データが十分に取られていないことも少なくありません。 しかし、私たちは、比較と介入群を両方トラッキングする方法や、時には簡素なランダム化比較実験(RCT)のような調査手法を採用しています。RCTは、介入する群としない群をランダムに分けて比較することで、介入の効果をより緻密に検証するものです。私たちは設立当初からインパクトの測定にこだわり、ビフォー/アフターを超えた効果検証のアプローチを導入することで、援助業界の効率化にもつながると考えていました。
このアプローチの強みは、「この課題がこのような形で解決された」というデータを元に示すことができる点です。このソーシャルセクターでは、何十年も前からデータの重要性が言われながらも、なかなかちゃんとした効果測定が実行されていません。そのため、資金提供者の方々は、我々のようなやり方を見ると、「こういうものが求められている、多くの組織がやるべきだ」と言ってくださいます。彼らは、本当の意味での社会解決に資金を提供したいと考えており、我々のデータに基づいたアプローチをまさに探していた、という感じです。
コペルニクの長期ビジョンとやりがい
ライフネシア:今後、コペルニクが目指す長期的なビジョンや、特に力を入れていきたい分野についてお聞かせください。

中村氏:引き続き、「途上国の課題を、いかによりよく、スマートに解決していけるか」という創業当初からのミッションを達成するために、「どのような仕掛けをすればシステムチェンジをうまく起こせるか」ということを意識して取り組んでいます。
具体的には、外部の組織にコペルニクで試して効果があると分かった解決策を「アダプション(採用)」してもらうことと、内部から事業を「スピンオフ」させることのバランスに注目しています。『ソリューションズカタログ』によるアダプションはまだ十分な成果が出ていないため、伝え方やアドボカシーの方法を工夫する必要があります。一方、スピンオフの数は現在4つですが、パイプラインに3~4つあり、来年には7~8つに増える見込みです。近い将来には、30~50のスピンオフ企業を目指したいと考えています。
コペルニク本体としては、引き続きこの「R&D(研究開発)」を続けていくことに注力します。うまくいかないものもあれば、うまくいくものもある。うまくいったものは他の団体に「真似」してもらうか、あるいは「スピンオフ」させる。このようにして、継続的に活動を広げ、規模を拡大していきたいと考えています。
ライフネシア:中村様ご自身にとって、コペルニクの活動を通じて最もやりがいを感じる瞬間はどのような時ですか?
中村氏:私も年齢を重ね、考え方も変わってきたように感じます。最近、最も嬉しいと感じるのは、若いメンバーが自ら主体的に活動してくれる姿を見る時です。特にスピンオフはまさにその形であり、CEOになる人たちは20代が多いです。彼らが目をキラキラさせながら「これをやりたい」と意欲を示し、実際にスピンオフして大きく成長していく姿を見ると、非常にやりがいを感じます。役割が人を育てると言いますが、彼らがCEOという立場になると驚くほど成長します。いかにそうした機会を提供し、彼らの才能を開花させられるかが、私がやるべきことだと感じています。以前はもっと自分が「ギラギラ」して何かを成し遂げようと思っていましたが、今は、自分一人でできることには限界があり、いかにムーブメントを作っていくかが大事だと感じるようになりました。
ライフネシア:社会貢献支援財団で表彰された後、何か変化はありましたか?
中村氏:はい、表彰いただいたことはインパクトがありました。社内外で話題となり、社会的な「箔」がついた、と言いますか、注目度が上がったと感じています。特に、プロジェクトメンバーにとっては、自分たちの活動が評価されたということが、自信やモチベーションに大きく繋がったと思います。
ライフネシア:コペルニクの活動に興味を持ち、何らかの形で貢献したいと考えているインドネシア在住の日本人や日系企業に向けて、具体的な協力の方法や期待する支援の形があれば、メッセージをお願いいたします。
中村氏:ありがとうございます。もちろん、資金提供は非常にありがたいです。それを超えて、企業様の場合は、社会課題に貢献する方法は様々あります。コペルニクとしては、日本国内外の企業とコラボレーションし、インドネシアにおける社会課題に関する製品やサービスのR&Dやテストを共に行うことを期待しています。既に製品を持っている企業、あるいは開発中の企業と、「この課題解決につながるのか」というテストを一緒に行い、製品化へと繋げるお手伝いができればと考えています。
また、寄付という形のご支援も大変ありがたいと思っています。私たちは元々、個人のクラウドファンディングから始まった団体でもあります。現在もマンスリー寄付(月額50ドルから)や、一口からの寄付を受け付けており、多くの方々から支援をいただいています。皆様の温かいご支援が、ラストマイルの人々の生活改善に直結しますので、ご協力いただければ幸いです。
あなたの周りのヒーローをご紹介ください。
公益財団法人 社会貢献支援財団では、コペルニクのような社会貢献者のご推薦を募集しております。誰かのために、社会のために頑張っているヒーローを是非ご紹介ください。
締め切りは、毎年10月31日(必着)です。
基本情報
| 財団名 | 公益財団法人 社会貢献支援財団 |
| fesco@fesco.or.jp | |
| Website | 公式HP |