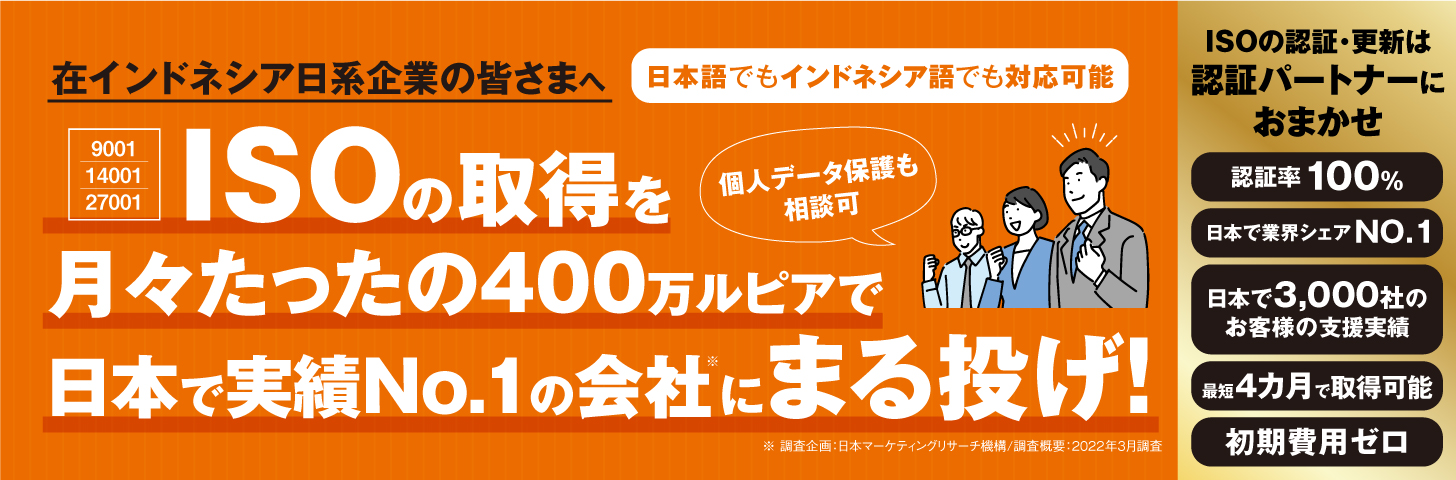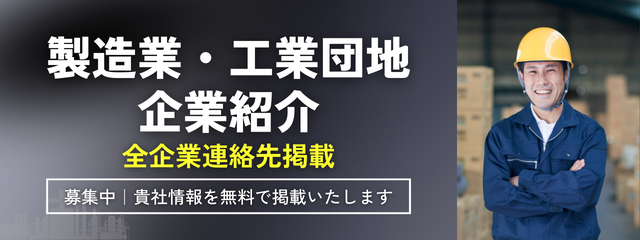情熱
着任して半年後、カード業界協会の総会が開催された。人脈を広げる絶好の機会だと思い参加、原稿棒読みだったが、インドネシア語でプレゼンをした。必死だった。「JCBはマーケットに戻ってきた。これからは本気だ。」と訴え、印象を植え付けることはできた。ここで築いた人脈が後述するBNI、CIMB NIAGAとのカード発行につながることになる。
着任して丁度1年後の2012年6月、BIIとのカード発行が再開した。過去とは全く異なるコンセプト、「プレミアム」でプラチナカードに日本ブランドならではの和食店での割引き、日系スーパーでの割引の特典を付けて売り出した。最初は日本人駐在員の方々に、その次は日本好きなインドネシア人富裕層に入会いただくことを見込んでいた。期待通り、カードは大好評だった。当時はまだまだJCBカードが使える店は少なかったが、特典に魅力を感じて沢山申込みをしていただいた。手ごたえを感じ始めた。
2014年4月、国営の名門銀行・BNI(Bank Negara Indonesia)との契約に成功。同行は、戦後初めてできた歴史ある銀行だ。BNIカード部門のトップに直談判し、何度も会って説得したところ、同社を通じてカード発行ができるようになった。
大手であるBNIとの提携により、業界のJCBを見る目が変わった。しかし、BNIとJCBの関係がうまくいかなければ、「BNIでもやっぱりダメか」と評価され、インドネシアでのJCBの展開は終わってしまう。絶対に失敗は許されない。
駐在開始から既に2年が過ぎていたが、今振り返れば、この時が最も緊張とストレスを感じていたと思う。BNIのカード部門トップの判断に同社の部下たちは納得していない。「VISAとMASTERだけで良いじゃん」とスタッフたちが考えているのが伝わってくる。どうしたら、JCBカードを受け入れてもらえるのか……。
トップと会談して、「JCBの優待、割引サービス、日本イメージを売りにして顧客を掴んでくれませんか」と頼み込んだ。BNIの地方支店を廻って、「JCBをお願いします」とあいさつをしてまわった。できることは何でもやった。

トップが部下に檄を飛ばしてくれたおかげで、カード発行枚数が目に見えて伸びた。目玉の割引サービスを全国各都市に広げ、スカルノハッタ空港にはラウンジも開設した。ラウンジ名に「JCBカード」と入るのは世界初、唯一だ。JCBカード会員はインドネシア全土、北はアチェ、東はパプアにまで広がった。
2014年にはCIMB NIAGAと、JCBでは世界初となる、日本国外では最高峰のプロダクトとなるUltimate(アルティメット)カードを生み出した。限度額は最高で20億ルピアという超富裕層向けカードである。
2015年には、タイを抜いて、東南アジア地域の現地発行カード売上1位に。BNIとの成功が効果を発揮し、同年Bank Mandiri, 2016年にはBRI(Bank Rakyat Indonesia)と立て続けに大手国営銀行とカード発行の契約を締結、そして遂には念願であったBCA(Bank Central Asia)ともカード発行再開の合意に至った。飛躍のポイントは、ニッチな分野に勝負を賭け、弱みを強みに変えてライバルが真似できない手を打ったことにある。
インドネシアでは、プレミアムブランドをキーワードに、プラチナカードだけを出した。つまりターゲットの絞り込みだ。世界中のJCBでここだけの一点豪華主義。こんなマーケットは他にはない。ターゲットにした客層は、プラチナカードを申し込める富裕層だけ。思い切った割引サービスや空港ラウンジなど、充実した特典はターゲットを絞るからこそできる技だ。ライバルの大手米系会社は発行枚数が多すぎてとても真似はできない。加盟店は少ない、知名度は低い、リソースは限られている、と三重苦で始まった戦いだが、インドネシアでのJCBカード発行枚数は16万枚に達した。2012年に発行事業に再参入して4年にしては、悪くない成果が出せたと自負しているが、まだまだ勝負はこれからだ。ブランドを更に広めるには、次のステージであるマスマーケットに切り込んでいく必要がある。
インドネシアで学んだことは、「自分の目で見たこと以外は信じるな」ということ。伝聞を事実と思い込んではいけない。推測でものを語らず、現場に足を運ぶことが大切なのだ。それから、やはり何事も「情熱」だ。本気で取り組めば、道は開ける。ラッキーだと思えることの裏には、努力と人との出会いがある。偶然はなく、必然しかないのだと思う。「一念岩をも通す」が私の座右の銘だ。

インドネシアでの駐在生活は、逃げ出したくなることも多かった。けれど、自分のベストを尽くし、がむしゃらに走ることで、多くの人に支えられ、ここまで辿り着くことができた。気が付けば、「いろいろな世界を見たい」という中学生の頃からの夢が叶っていた。
(2017年:週刊Lifenesiaに掲載)