東京の街角を少し散策すると、必ずといっていいほど、黒い箱型のバックパックを背負い、自転車で颯爽と駆ける人を見かける。「Uber Eats」に代表されるフードデリバリーサービスは、コロナ禍も手伝ってその存在感を増し、今や日常生活に欠かせないものとなりつつある。
インドネシアでも、インドネシアの大手ITグループGoToが運営するGojekの「go food」とシンガポールに本拠を置くGrabの「Grab Food」の2つがフードデリバリー業界の双璧をなす。2022年の流通取引総額(GMV)ベースで、前者が44%、後者が49%。まさに2強状態で覇権を争っている。
そんなフードデリバリーだが、利用している方も多いだろう。遠方にある飲食店にも注文でき、安い配達料で自宅や勤務先などに配達してくれる。支払いもオンライン決済可能なので、直接受け取らず、アパートのレセプションに預けることもできるし、渋滞激しい当地では非常に便利と重宝されている。
加盟飲食店も、道端の屋台から高級レストランまであり、インドネシア料理はもちろん、和食やイタリアン、コーヒーやデザートなどお目当てのものが見つからないことはほとんどない。また、配達者の名前や顔写真が明記され、配達中の位置もGPS確認することができる。
こんな便利なサービスを安価で利用できるのには感謝しかないが、利用者側の姿勢について耳を疑うような話を耳にすることがある。サービスには、配達者に対してチップを追加する機能が備わっている。最低1,000ルピア(約9円)から設定されている。もちろん「チップ」なので、義務でもなければ、強要されるものでもない。ただ、どんな渋滞でもどんな雷雨でも確実に届けてくれる配達者に対して、10,000ルピア程度は払うようにしている。安すぎる配達料から、彼らの歩合を推察するのは難しい事ではないからだ。
飲食店がモールなどに入居している場合、料理を待つ間の駐車料金が発生することがある。その場合はたいてい、メッセージでその旨を連絡してきてくれる。だいたい2,000ルピア程度だが、それを了解しながら実際払わない不心得者がいるらしい。彼らの生活を考えれば死活問題だ。嫌なら自分で行けと言いたいが、そんな人間には不毛な期待だ。
2022年のGMVは2社合わせて41億9千万米ドルにもなる巨大市場。だが配達者を守る小さな取り組みにも目を向けてほしい。そう切に願う。
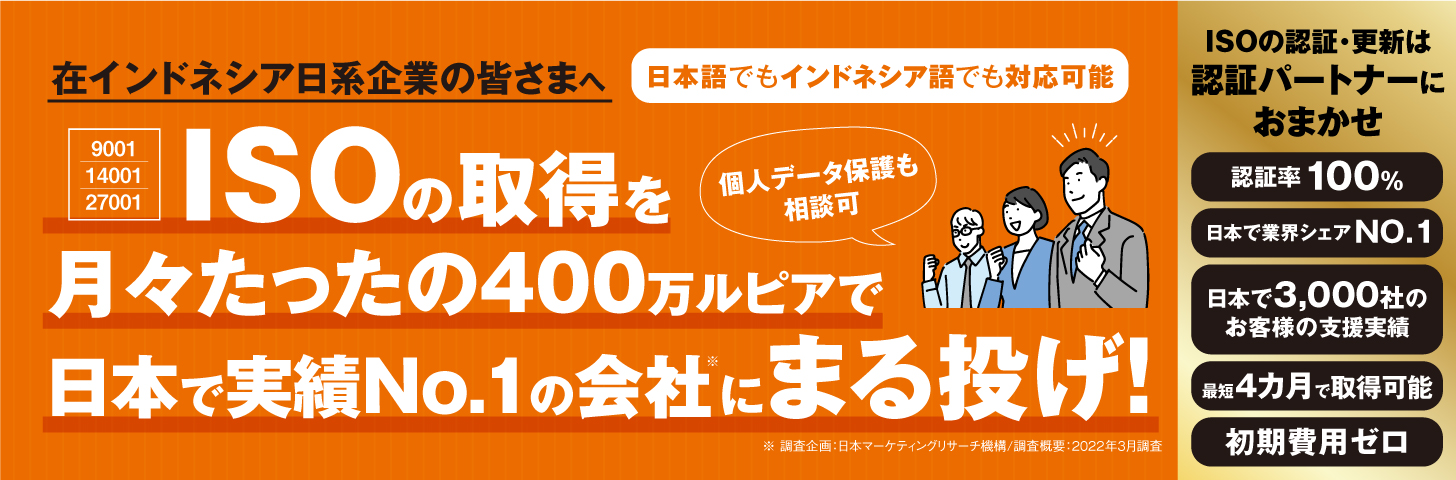









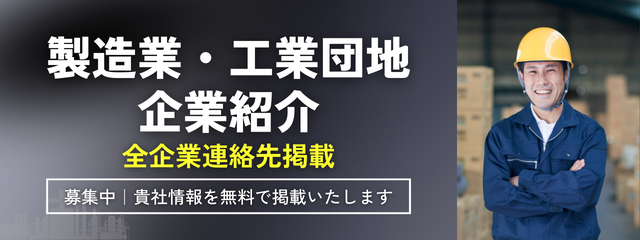









月刊誌やネット版ニューズウィーク、JBPress、現代ビジネス、東洋経済オンライン、Japan in depth などにインドネシアや東南アジア情勢を執筆。